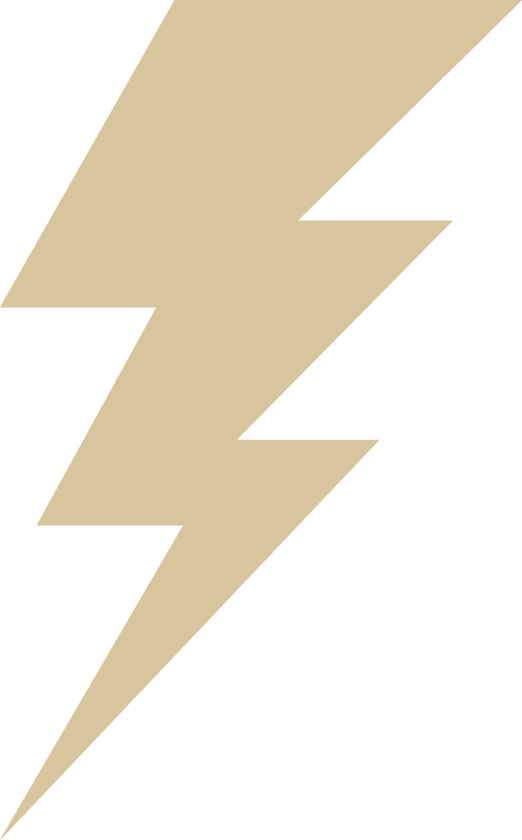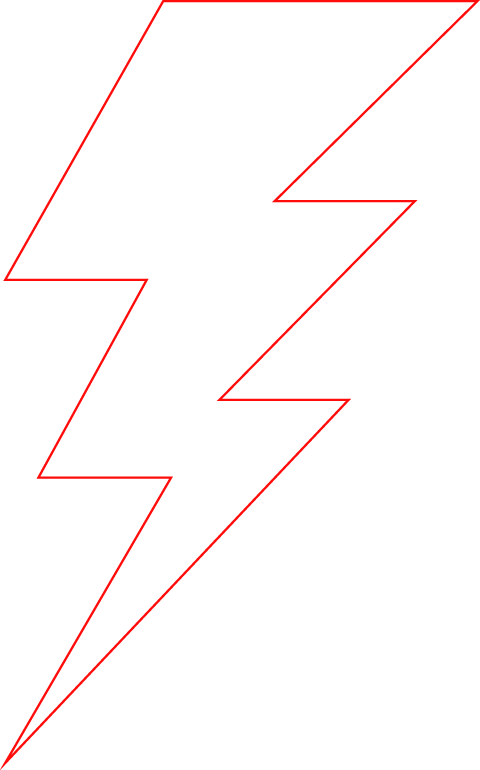院庄林業株式会社
常務取締役・管理本部長 田原 義彦
循環が未来を育てる。院庄林業、木と共に挑み続ける70年
木を育て、伐採し、加工し、建てる──そして再び植える。
院庄林業株式会社は、岡山県津山市を拠点に、木材の"すべて"を自社で担う総合木材メーカーだ。1955年の創業から70年、地域に根ざしながら、山林経営から製材、集成材製造、プレカット加工、住宅建築までを一気通貫で手がけてきた。
日本で初めて低温除湿乾燥機を導入し、乾燥技術で業界に名を馳せた同社。国産ヒノキの無垢材ブランド「匠乾太郎」は、その技術の結晶だ。だが、院庄林業の真の強みは、数字や設備だけではない。「改善することが仕事」という文化が組織に根付き、年齢や役職に関係なく、誰もが挑戦できる風土がある。
さらに、補助金に頼らない「匠乾太郎 植林基金」を立ち上げ、木育を通じて次世代に森の循環を伝え、メディアを生み出して林業の魅力を発信する。その視線は世界へと向かい、フィンランドやパラグアイとの技術交流も進めている。
津山という地から世界へ。挑戦が熱狂を生み、熱狂が次の挑戦を生む。院庄林業の歩みは、木と人、そして未来をつなぐ循環の中に息づいている。
2025年8月より参加院庄林業株式会社 常務取締役・管理本部長 田原 義彦 様
- 氏名
- 常務取締役・管理本部長 田原 義彦
- 会社名
- 院庄林業株式会社
- 出生年
- 1974年
- 座右の銘
- You never fail until you stop trying.
- 略歴
-
- 1997年 愛媛大学 理学部化学科 卒業
- 1997年 院庄林業株式会社 入社
- 2010年 清水工場で生産体制を整備、生産量4倍に
- 2012年 津山新工場建設プロジェクト責任者に就任
- 2013年 岡山工場 工場長に就任
- 2023年 常務取締役に就任
津山という地域、ヒノキという資源
70年続く木との対話
院庄林業株式会社の歴史は、昭和30年に始まった。創業者である武本平八郎氏が、岡山県北部の鏡野町にて個人で製材業を起こしたのが出発点だ。山深い土地で木を切り、製材し、売る。当時、山林を所有する家が木材を生業とすることは、農家が野菜を育てるのと同じく、ごく自然なことだった。やがて事業拡大のため、より利便性の高い津山市二宮へと拠点を移し、株式会社を設立した。
津山ならびに岡山県北は、林業にとって恵まれている地域だ。岡山県北部は古くから林業が盛んで、豊富なヒノキが育ち、木材を扱うことは「当たり前」として根付いていた。実際、津山地域には大小さまざまな製材所が点在し、林業が地場産業として定着。技術や知識が地域に蓄積されており、業界への理解が深い。この土壌が、院庄林業の成長を支えてきた。
現在、同社は年間総製材量88,000㎥、年間総伐採実績50,000㎥、従業員数350名を擁する国内有数の木材メーカーへと成長している。2019年度から2021年度の平均年間売上は295億円、出荷する商品の種類は2,000種に及ぶ。
この成長を支えている一人が、常務取締役・管理本部長の田原義彦氏。工場運営から生産管理、さらには経営戦略まで、会社の中枢を担う人物だ。彼が語る院庄林業の強みは、数字以上の「質」にある。同社が木材業界で知られるようになった大きなターニングポイント、それは「乾燥技術」だった。
乾燥という技術
日本初が切り拓いた道
昭和57年、院庄林業は日本で初めて低温除湿乾燥機を導入した。当時、木材は屋外に置いて自然乾燥させるのが当たり前だった時代に、同社は「乾かす」ことに技術を見出したのだ。
ではなぜ、乾燥した木材が良いのか 。水分を多く含んだ木材は、乾燥の過程で収縮し、ひずみ、割れる。そのため、従来の芯持ち材には「背割り 木材の中心部に切れ目を入れる処理 」が必要だった。だが、この背割りが、経年による反りや亀裂の原因となる。十分に乾燥させた木材は背割りが不要になり、強度が保たれ、建築資材としての信頼性が格段に高まるというわけだ。
「乾燥って、極端な話、木にドライヤーでビューっと風を当てたら乾くんですよ。でもそのままやっちゃうと、どこかでバキッと割れる。温風を当てながら、湿度も入れながら、でないと。この乾かし方にやっぱり技術がある」。
温度と湿度を緻密にコントロールする必要があるというわけだ。何度で、湿度何パーセントで、どれくらいの時間をかけるのか。材料によっても違う。地域によって木の水分量は異なり、樹種によっても性質は変わる。その判断が、製品の質を左右する。
1990年には、財団法人日本住宅木材技術センターより、日本で初めて建築用針葉樹乾燥処理材AQ認証工場の指定を受けた。そして、乾燥技術を核に生まれたのが、国産ヒノキの天然無垢材ブランド「匠乾太郎(たくみかんたろう)」である。含水率15%という数値は、木材が建築資材として安定する基準を満たす証だ。院庄林業という名が業界に知られるようになったのは、この「匠乾太郎」の存在が大きかった。



若き青年の歩み
静岡で生産量を4倍にした男
田原氏が院庄林業に入社したのは1997年。当時22歳。入社の経緯は、計画的とは言い難いものだった。
「私は理学部化学科を卒業したので、林業は全く関係ありませんでした」。
愛媛大学で化学を学び、4年生になっても就職活動を一切していなかったと言う。8月、9月になっても何も決まっていない。そんな彼に声をかけたのが、津山綜合木材市場に勤める母だった。この市場には院庄林業も木材の買い付けで頻繁に出入りしており、縁が深い。その縁で院庄林業に誘われ、面接を受けた。興味があったわけでもなく、会社名も知らないところからのスタートだった。
最初の赴任地は静岡県の清水工場。稼働してまだ半年ほどの新設ラインで、フィンガージョイント 短い木を繋いで長くする工程 を担当することになった。だが、設備も人員も整っておらず、まさに“ゼロからの立ち上げ”。「岡山弁で“無茶苦茶”のことを“ワヤ”って言うんですけど、もうワヤなんですよ(笑)」と笑う。
「今は絶対そんなことないんですけどね」と前置きしつつ、当時を振り返る。マニュアルもなく、手探りで現場を覚えるしかない日々だった。
だが、田原氏はそこで着実に成果を積み重ねていく。12年間の在籍中に、現場作業から生産管理、営業まで幅広く経験を重ねた。「もっと早く」「もっと多く」を合言葉に、機械配置を見直し、作業フローを一から設計し直す。小さな改善の積み重ねが、やがて大きな結果を生んだ。清水工場の生産量は、月産3,000㎥から12,000㎥へ 4倍の伸びを達成したのである。
そして2012年、田原氏に大きな転機が訪れる。津山に新工場を建設する その責任者に抜擢されたのだ。レイアウト設計から機械選定、組み立てに至るまで、すべてを自らの手で構想した。数十億円規模のプロジェクトを、30代前半の社員に託す。当時、それは社としても異例の決断だった。
「普通、任せないと思うんですよ」と田原氏は笑う。だが、会社は彼を信じた。完成した工場の工場長に就任したのは、35歳のとき。驚きと責任、そして任された誇り そのすべてが、彼の言葉の端々から伝わってきた。
改善が仕事
現場を動かす哲学
35歳で工場長に就任してから、田原氏の視線は「人」と「仕組み」に向かうようになった。どうすれば現場をもっと良くできるか その答えを探し続けた先にあったのが、「改善」という考え方。
院庄林業の現場には、「改善することが仕事」という文化が根付いている。新人もベテランも関係ない。どんな立場でも、昨日より良くすることが求められる。
「日常の仕事はもちろん大事なんですけど、改良することが仕事に本当の価値を生む」。田原氏はそう語る。
どれほど優れた機械を導入しても、それを動かすのは人である。「機械とか組み方を真似しても、人のソフトができないと上手く回っていかない」。全員が同じ方向を向いていなければ、工場は機能しない。「立ち上げの時は、反対派が何人かいるのが当たり前。そういう人たちと何度も話をして、少しずつ方向を合わせていく。それが大変でもあり、やりがいでもあります」。
静岡から津山に戻った当初、田原氏は現場の社員にとって“よそ者”だった。100人規模の工場で信頼を得るのは容易ではなかったが、対話を重ね、少しずつ信頼を積み重ねていった。
そうした姿勢を見ていた社員から、「職位が上がっても、20代の時の田原さんのままだね」とよく言われるという。
彼がリーダーとして大切にしているのは「自然体」と「好奇心」。肩書きが変わっても、姿勢や振る舞いは変えない その一貫した在り方が、組織の信頼を支えている。
院庄林業には、年齢や勤続年数にとらわれず、実力で役割を任せる文化がある。
これまでに就任した最年少マネージャーは27歳。若手であっても、良い提案はすぐに採用される。
「改善することが仕事」という信念は、田原氏個人の哲学であると同時に、会社そのものを動かすエンジンでもある。




一気通貫という強み
山から家まで、すべてを担う
院庄林業の強みは、技術や設備に留まらない。木を「育てる」から「使う」まで 山林の育成・伐採、製材、集成材製造、プレカット加工、住宅資材販売、建築、リフォームに至るまでを、自社で完結させる“垂直統合型のビジネスモデル”にある。
この体制により、窓口は一本化され、工程のロスが減り、品質管理も一貫する。発注側にとっては、最初から最後まで安心して任せられるワンストップの相手だ。全国的にも、上流から下流までを自社でつなげる企業は稀少。だからこそ、この“木の全領域を束ねる力”が、院庄林業の決定的な競争優位になる。
そして近年、同社がとくに注力しているのが「非住宅分野」だ。学校や銀行、コンビニなど、これまで鉄やコンクリートが主流だった建物の木造化を推進している。現在、日本における非住宅建築の木造率はわずか10~15%。だが、国は脱炭素社会の実現に向け、公共建築物の木造化を積極的に後押ししており、今後その比率は確実に上昇していく。
人口減少によって住宅市場の縮小が避けられない中、非住宅木造は、次代を支える新たな柱となる。
田原氏は語る。
「木造化を進めること自体が、広い意味で環境に貢献するということ。木は生えてから40年くらいまではCO₂をよく吸収しますが、成長しすぎるとその力が落ちてくる。だからこそ、伐って使って、また植える。この循環を続けることが、森林を健全に保つ鍵なんです」。
木を伐り、使い、また植える 。
その循環を自ら実践する院庄林業は、単に木を加工する企業ではない。「森を育てる企業」として、環境と地域の未来を見据えている。
補助金に頼らない植林基金
SDGsを自らの手で
院庄林業が2021年に立ち上げた「匠乾太郎 植林基金」は、同社の理念を象徴する取り組みだ。国産ヒノキの天然無垢材ブランド「匠乾太郎」の売上の一部を、植林費用として積み立てる。伐採後に自ら植え、育て、次代へ資源をつなぐ 。この循環を補助金に頼らず、自立した仕組みとして実現している点に、院庄林業らしい哲学がある。
「SDGsって、補助金を活用することが目的になってはいけないと思うんです。設備投資などの初期費用を支援してもらうのはいい。でも、利益を補填するために依存してしまうのは違う。ビジネスの仕組みの中にSDGsを組み込むことが大切なんです」。
日本の人工林の多くは、伐採後に植え戻しがされず、荒れたままになっている。法律上は「天然更新」という建前があるが、実際には放置された森林も多い。そのままでは木は細り、山は痩せ、資源としての価値を失ってしまう。
だからこそ、院庄林業は自ら植える。
久米工場の敷地内に苗木畑を設け、社員が一本一本、草を取り、水をやり、成長を見守る。山林管理や伐採の担当者だけでなく、事務や設計部門の社員も関わることで、「木を育てる」という営みが組織全体に根づいていくのだ。
2020年には、クラウドファンディングで「3,000本のヒノキの苗木を植えよう!みんなでつくる50年後の森」を実施し、目標金額を達成。岡山県鏡野町の1ヘクタールの土地に苗木を植え、支援者と共に森づくりを進めてきた。「未来の森を、自分たちの手で残す」。
その決意こそ、院庄林業が掲げる“木とともに生きる”という理念のかたちである。
そしてこの思想は、森を越えて人へ 次世代への教育や発信活動へと広がっている。


未来を育む発信
木育とメディアが繋ぐもの
森を育てる企業として、院庄林業が次に見つめるのは「人の“気付き”を育てる」ことだ。その象徴が「木育」である。木育とは、木を通じて人と森の関係を学ぶ教育活動。院庄林業では、津山市内外の子ども施設、小中高校や地域イベントを通じて、子どもたちに“木の循環”を伝えている。伐って、使って、また植える 。この当たり前のサイクルを次世代に受け継ぐことが、未来の森林を守る第一歩だ。
「自分たちの世代は、木を切って使ってまた植えるなんて教わってこなかった。だからこそ、子どもたちに伝えたいんです」と田原氏は語る。木は、唯一人の手で再生できる資源。だが、循環を止めれば森は荒れ、命の連鎖も途切れる。だからこそ、「木を使うことは森を守ること」という考え方を、子どもたちに体験を通して伝えていく。
こうした取り組みの背景には、BtoB企業として一般の人と接する機会が限られていたこと、地域との関わりが希薄になりつつあったことへの危機感がある。「地域に恩返しをしたい」 その想いこそが、木育活動の原動力になっている。
実際に同社では、地元の少年野球チームや幼稚園を対象にしたワークショップを開催し、山や工場の見学、木を使った工作体験などを通じて、子どもたちが木と身近に触れ合う機会をつくっている。教えるというよりも、「気づいてもらう」。そんなスタンスで、地域に根ざした“木育”に取り組み続けているのだ。
こうした教育活動と並行して、院庄林業は「発信」にも力を注ぐ。
同社が全面協賛するウェブマガジン『WHOLE EARTH MAGAZINE』は、主に学生を取材対象に、林業・農業・土壌・海洋・生物学などを横断し、「地球環境に資する学び」をアーカイブして届ける全国初の環境系WEBメディアだ。若い世代の探究や実践を拾い上げ、環境とともに生きる視点を社会に開く場として運営されている。
また2022年には、地域と林業の魅力を若い世代に伝えるため、ビジュアルブック『NORTHERN FORESTRY MAGAZINE』を発刊。ファッションカルチャー誌「PLUG MAGAZINE」と協働し、林業の世界をカルチャーとして表現したこの試みは、業界内外から大きな注目を集めた。伝統産業が自らメディアを生み出し、地域や世代を超えて発信する 院庄林業ならではの、新しい挑戦のかたちである。
木を使うだけではなく、木の魅力を伝え、木の文化を育てていく。
木育という“種まき”と、メディアという“発信”。
その両輪が、森と人の未来を結びつけている。


岡山から世界へ
木という資源が繋ぐネットワーク
院庄林業の視線は、今や世界に向かっている。
フィンランドやパラグアイなど、各国の現場に足を運び、木材資源の多様化と技術の最前線を自らの目で確かめているのだ。県北の一企業がここまでグローバルに動く その背景には、次代のものづくりを支える明確な意志がある。
ひとつは、木材資源の安定供給だ。日本にも森林資源はあるが、需要の変動や環境政策の影響を考えれば、海外からの調達ルートを複数確保することが不可欠だ。「一国だけに頼りきりではいけない。複数の選択肢を持つことが、結果的に国内の安定にもつながる」と田原氏は語る。
もうひとつは、世界の技術を学ぶこと。フィンランドやドイツ、ノルウェーといった林業先進国では、林産業が国の基幹産業と捉えられており、製材や加工の機械技術は世界トップクラスにある。「ヨーロッパの製材企業の中には、日本で言う“TOYOTA”のような存在感の会社もある。規模も発想もまったく違うんですよ」と田原氏。現地の仕組みや工場を訪ねることで、日本ではまだ実現していない効率化や自動化の可能性を感じ取っている。
2025年の大阪・関西万博では、フィンランド館が“木”をテーマに展示を行っていた。田原氏もそれを見に訪れ、「ヨーロッパでは木の地位が高い」と改めて感じたという。戦後の日本が鉄やコンクリートに重きを置いてきたのに対し、欧州では“木が未来を支える素材”として社会に根付いている。だからこそ、現地に足を運び、最先端を知ることに意味があるのだ。
そしていま、新たに始まったのが南米・パラグアイとの連携だ。今年、同国政府の要請を受け、院庄林業は現地で製材や加工の技術協力を検討。成長が早く、建築材としても優れたユーカリの活用をめぐり、国家レベルで協議が進められている。
同年には政府関係者が津山の工場を視察し、ペニャ大統領からも直接招請を受けた。
地方企業でありながら、世界の森林資源と直接向き合う その姿勢こそ、院庄林業の新たな挑戦を象徴している。
“今”を積み重ねる
挑戦が熱狂を生む現場
院庄林業の現場には、確かな熱がある。改善を重ね、新しいことに挑み、結果を出し、また次へと向かっていく その絶え間ない挑戦の連続こそが、この会社の「熱狂」を形作っているのだ。
「自然体」「好奇心」「とりあえずやってみる」 。田原氏が体現するこの姿勢は、院庄林業という組織全体に根付いている。
彼にとっての「熱狂」とは、新しいプロジェクトに挑み、結果が出た瞬間。
「新しい工場を作るとか、新しいソリューションを組み立てるとか。大変なんですけど、終わった後に仲間と飲みに行って、『あれは良かったな』って振り返る。そういう時間が、結局一番いいんだと思います」。
挑戦の先にある達成感、そしてチームで共有する喜び それが会社を動かすエネルギーとなっているのだ。
その姿勢は、仕事の枠を超える。パラグアイで政府要人と協議する傍ら、現地のマルベックという赤ワインに出会った。「仕事で訪れた国で、まだ知らない“興味”や“美味しさ”に出会うのが楽しい」と田原氏は笑う。どんな場所でも”発見”を楽しむ心 それが、改善を続け、挑戦を重ねる原動力になっている。
若い世代へのメッセージを尋ねると、こう答えてくれた。「今できないことは老後にもできない。だから、今の自分の一歩外まで行けるよう心がけてほしい」。
その言葉は、院庄林業という組織そのものの姿勢でもある。
木を学び、木と働き、木に挑み続ける。その連鎖の中で、院庄林業は進化を続けている。津山という地から世界へ。一人ひとりの挑戦が重なり、組織を動かし、未来を開いていく。挑戦が熱狂を、熱狂が次の挑戦を生む その循環が、院庄林業の未来を切り拓いている。